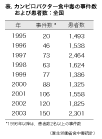(IDWR 2005年第19号)
カンピロバクター属菌は2004年現在、17菌種6亜種3生物型から構成されている。ヒトのカンピロバクター感染症は胃腸炎症状を主たる臨床像とし,その原因菌の95〜99 % はCampylobacter jejuni subsp. jejuni(以下C. jejuni )で、C. coli は数%に止まる。また、敗血症や髄膜炎、膿瘍などの検査材料から分離されるカンピロバクターはC. fetus subsp. fetus であることが多い。カンピロバクター感染症はC. jejuni 腸炎、またはC. jejuni 食中毒とほぼ同義語と考えてよく、ここではその周辺に焦点をあてて概説する。
疫 学
C. jejuni はC. coli と共に1982年、食中毒起因菌に指定されて以来、食中毒事例数においてサルモネラ、腸炎ビブリオ、黄色ブドウ球菌に次ぐ発生頻度を示している。しかし、C. coliによる集団食中毒事例は極めて少ない。C. jejuni 食 中毒は欧米諸国と同様、近年我が国においても増加傾向にあり、厚生省(当時)の食品衛生調査会食中毒部会(平成12年2月25日)でもその対策が急務であ る旨、提言がなされている。全国における本食中毒の年間事例数(1996年以降は患者数2名以上)は、厚生労働省食中毒統計によると、1995〜1996 年では20〜46件であったが、1997年頃より増加傾向を示し、2003年には150件にも達している(表)。学校施設内および学外行事などでの大規模 食中毒事例が減少し、飲食店などを原因施設とした小規模事例の占める割合が急増してきたため、患者数の大幅な増加はなく、1,300〜2,500人前後を 推移している。一方、散発例での本菌食中毒発生状況をみると、患者は女性より男性に多く、年齢層では10〜20代にピークが認められている。成人散発例で の本菌検出率は10%前後であり、小児では約15〜25%で腸炎原因菌の第1位を占めているが、受診当初は感冒と診断されることも多く、実際の患者数はか なりの数に上るものと推察される。また、入院症例も10歳以下の低年齢層に多い(感染性腸炎研究会資料)。
| 一般に、細菌性食中毒は夏季に多発し、冬季に減少するが、本食中毒においては様相を異にして、その発生は5〜6月に多く、7〜8月はやや減少、再び9〜10月頃に上昇傾向を示している。しかし、東京都内では1999年以降、冬季の発生が著しく増加している。 | |
| 表. 表カンピロバクター食中毒の事件数および患者数:全国 |
C. jejuni 食中毒発生時における感染源の特定は極めて困難である。それは少量感染(500〜800個/ヒト)が成立す ること、潜伏期間が比較的長いこと(2〜5日)、加えて、通常の大気条件下では本菌が急速に死滅する生理学的特徴に起因する。しかし、患者並びに推定原因 施設等の疫学調査結果からは、鶏肉調理食品の喫食、及びその調理過程の不備が原因であったことが強く示唆されている。欧米では生牛乳による事例もあるが、 我が国では加熱殺菌乳が流通しており、同様な事例はみられていない。この他、井水、湧水および簡易水道水を感染源とした水系感染事例が、我が国では少なく とも12例確認されており、その原因の大部分は不十分な消毒であった。
病原体
| C. jejuni は長さ0.5〜5μm、幅0.2〜0.4μmのグラム陰性らせん状桿菌である。両極にそれぞれ1本の鞭毛を持ち、所謂コルクスクリュー様の独特な運動を活発にする(写真)。 |  |
| 写真. Campylobacter jejuni の電子顕微鏡像 (東京都健康安全センター) |
本菌の発育には微好気条件(酸素濃度:5〜10%)が必須で、発育温度域は34〜43℃、炭水化物は好気・嫌気的にも利用できず、 NaCl濃度0.5%前後を至適とした好塩性を有する。本菌はウシ、ヒツジ、野鳥及びニワトリなど家禽類の腸管内に広く常在菌として保菌されており、C. coli はブタでの保菌率が極めて高いことを特徴とする。
臨床症状
症状は下痢、腹痛、発熱、悪心、 嘔吐、頭痛、悪寒、倦怠感などであり、他の感染型細菌性食中毒と酷似するが、潜伏期間が一般に2〜5日間とやや長いことが特徴である。感染性腸炎研究会資 料によると、入院患者の98%に下痢が認められ、その便性状は水様便(87%)、血便(44%)、粘液便(24%)である。特に粘血便がみられる場合は、 細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌、腸炎ビブリオ、サルモネラ等による腸炎との鑑別を要する。下痢は1日に10回以上に及ぶこともあるが、通常2〜6回で1〜 3日間続き、重症例では大量の水様性下痢のために、急速に脱水症状を呈する。また、腹痛は87%、嘔吐は38%にみられた。発熱時の平均体温は38.3℃ で、サルモネラ症に比べるとやや低い。
病原診断
C. jejuni 感染症の診断は臨床症状からは困難で、糞便等から本菌を分離することが最も確実である。培養は微好気培養により最低2日間(37〜42℃)要する。本菌の 同定には通常3〜5日間程度必要であり、迅速性・正確性を期するために、PCR法等の遺伝子診断技術が必要不可欠となっている。
治療・予防
患者の多くは自然治癒し、予後 も良好である場合が多く、特別治療を必要としないが、重篤な症状や敗血症などを呈した患者では、対症療法と共に適切な化学療法が必要である。第一選択薬剤 としては、エリスロマイシン等のマクロライド系薬剤が推奨される。セフェム系薬剤に対しては自然耐性を示すため、治療効果は望めない。
ニューキノロン系薬剤に対しては近年耐性菌が増加しており、世界的な問題となっている。私共の調査においても、NFLX, OFLX, CPFX, NAの4剤に対する耐性株出現頻度は、調査開始時(1993〜1994年)は15%程度であったが、1999年には28.7%、2000年29.5%と増 加傾向を示し、その後2003年まで30%前後を推移している。従って本剤を使用する際は、このことを念頭に入れた処方が必要であろう。
本菌感染症の予防は、食品衛生の面からみると、他の細菌性食中毒起因菌と同様に、獣肉(特に家禽肉)調理時の十分な加熱処理、また、調理 器具や手指などを介した生食野菜・サラダへの二次汚染防止に極力注意することである。また、本菌は乾燥条件では生残性が極めて低いことから、調理器具・器 材の清潔、乾燥に心掛けることも重要である。一方、食品の嗜好面から は、生肉料理(トリ刺し、レバ刺し等)の喫食は避けるべきであろう。その他、イヌやネコ等のペットからの感染例も報告されており、接触する機会の多い幼小 児及び高齢者等に対して啓発を図ると共に、ペットの衛生的管理が必要である。
合併症
C. jejuni 感染症の一般的な予後は、一部の免疫不全患者を除いて死亡例も無く、良好な経過をとる。しかし、近年本菌感染後1〜3週間(中位数:10日間)を経てギラ ン・バレー症候群 (GBS)を発症する事例が知られてきた。GBSはフィッシャー症候群など複数の亜型があるが、基本的には急性に四肢脱力を主徴とする、運動神経障害優位 の自己免疫性末梢神経障害である。GBS患者の約30%では、GBS発症前1ヵ月以内に本菌感染症の罹患が認められており、その発症メカニズムの主因とし て、菌体表層の糖鎖構造と運動神経軸索に豊富に分布するガングリオシドとの分子相同性が指摘されている。GBSはこれまで予後良好な自己免疫疾患として捉 えられていたが、C. jejuni 感染症に後発するGBSは軸索型GBS(AMAN:acute motor axonal neuropathy)で重症化し易く、英国のデータでは発症1年後の時点においても、4割程度の患者に歩行困難などの種々の後遺症が残ると言われてい る。また、一部患者では呼吸筋麻痺が進行し、死亡例も確認されている。GBSの罹患率は諸外国でのデータでは、人口10万人当たり1〜2人とされている。 我が国での発生状況については報告システムがなく、実数は不明であるが、年間2,000人前後の患者発生があるものと推定されている。
C. jejuni 感染症に後発するGBSは、これまで散発例として確認されてきた。しかし、1999年12月東京都において、C. jejuni 集団食中毒患者19名中、1名のGBS患者の発生が確認されたが、 これは諸外国でもほとんど例がない。この事例は、GBS発症にC. jejuni 感染症と患者の免疫学的背景とが関与していることを立証した、極めて貴重なものであった。
感染症法における取り扱い(2012年7月更新)
「感染性胃腸炎」は定点報告対象(5類感染症)であり、指定届出機関(全国約3,000カ所の小児科定点医療機関)は週毎に保健所に届け出なければならない。
届出基準はこちら
食品衛生法における取り扱い
本食中毒が疑われる時は、食品衛生法第58条に基づき24時間以内に保健所長に届ける。
(東京都健康安全研究センター・微生物部 高橋正樹 横山敬子)