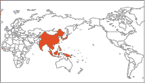(IDWR 2002年第1・2合併号掲載)
主にコガタアカイエカによって媒介され、日本脳炎ウイルスによっておこるウイルス感染症であり、ヒトに重篤な急性脳炎をおこす。日本脳炎ウイルスはフラビウイルス科に属するウイルスで、1935 年ヒトの感染脳から初めて分離された。
疫 学
|
日本脳炎は極東から東南アジア・南アジアにかけて広く分布している(図1)。過去日 本脳炎の報告がなかったパプアニューギニアにおいても、1997年に患者の報告がなされた。1995年にオーストラリアのトレス海峡Badu島、1998 年にBadu 島・ヨーク岬半島にて日本脳炎患者の発生が報告され、アジア以外の地域への日本脳炎ウイルスの広がりが明らかになった。 |
|
|
図1. 日本脳炎の発生地域 |
世界的には年間3〜4万人の日本脳炎患者の報告があるが、日本と韓国はワクチンの定期接種によりすでに流 行が阻止されている。日本では、1966 年の2,017人をピークに減少し、1992年以降発生数は毎年10人以下であり、そのほとんどが高齢者であった。しかし、1999年以後、10歳代2 例、30歳代・40歳代各1例と比較的若年の患者が発生していることは注目される。
厚生労働省では毎年夏に、ブタの日本脳炎ウイルス抗体獲得状況から、間接的に日本脳炎ウイルスの蔓延状況を調べている。それによると、毎夏日本脳炎ウイルスを持った蚊は発生しており、国内でも感染の機会はなくなっていない。
病原体
日本脳炎は、フラビウイルス科に属する日本脳炎ウイルスに感染しておこる。このウイルスは、伝播様式からアルボウイルス(節足動物媒介性ウイルス)とも分 類される。日本などの温帯では水田で発生するコガタアカイエカが媒介するが、熱帯ではその他数種類の蚊が媒介することが知られている。ヒトからヒトへの感 染はなく、増幅動物(ブタ)の体内でいったん増えて血液中に出てきたウイルスを、蚊が吸血し、その上でヒトを刺した時に感染する。ブタは、特にコガタアカ イエカに好まれること、肥育期間が短いために毎年感受性のある個体が多数供給されること、血液中のウイルス量が多いことなどから、最適の増幅動物となって いる。ヒトで血中に検出されるウイルスは一過性であり、量的にも極めて少なく、自然界では終末の宿主である。また、感染しても日本脳炎を発病するのは 100〜1,000人に1人程度であり、大多数は無症状に終わる。
フラビウイルス属のなかでも、特に日本脳炎ウイルス、西ナイルウイルス(1999 年より夏期にニューヨーク・米国東海岸で流行している)、セントルイス脳炎ウイルス、マレー渓谷脳炎ウイルスは相同性が非常に高く、これらは日本脳炎血清 型群(Japanese encephalitis serocomplex )とよばれる。
臨床症状
日本脳炎の潜伏期は6 〜16 日間とされる。本症の定型的な病型は髄膜脳炎型であるが、脊髄炎症状が顕著な脊髄炎型の症例もある。典型的な症例では、数日間の高い発熱(38 〜40 ℃あるいはそれ以上)、頭痛、悪心、嘔吐、眩暈などで発病する。小児では腹痛、下痢を伴うことも多い。これらに引き続き急激に、項部硬直、光線過敏、種々 の段階の意識障害とともに、神経系障害を示唆する症状、すなわち筋強直、脳神経症状、不随意運動、振戦、麻痺、病的反射などが現れる。感覚障害は稀であ り、麻痺は上肢で起こることが多い。脊髄障害や球麻痺症状も報告されている。痙攣は小児では多いが、成人では10%以下である。
検査所見では、末梢血白血球の軽度の上昇がみられる。急性期には尿路系症状がよくみられ、無菌性膿尿、顕微鏡的血尿、蛋白尿などを伴うことがある。髄液 圧は上昇し、髄液細胞数は初期には多核球優位、その後リンパ球優位となり10〜500程度に上昇することが多い。1,000以上になることは稀である。蛋 白は50〜100mg/dl 程度の軽度の上昇がみられる。
死亡率は20〜40%で、幼少児や老人では死亡の危険は大きい。精神神経学的後遺症は生存者の45〜70%に残り、小児では特に重度の障害を残すことが多い。パーキンソン病様症状や痙攣、麻痺、精神発達遅滞、精神障害などである。
病原診断
日本脳炎ワクチン未接種者や不完全接種者で夏期に発生した脳炎患者の場合には、必ず日本脳炎を考慮する必要がある。
日本脳炎が疑われた場合は、血清の抗体価を調べる。赤血球凝集抑制(HI)試験、補体結合(CF)試験、 ELISA 法、中和試験などがある。HI、CF抗体で確定診断する場合、単一血清ではそれぞれ1:640,1:32以上の抗体価であることが必要である。急性期と回 復期のペア血清で抗体価が4倍以上上昇していれば、感染はほぼ確実となる。海外渡航歴がなく、IgM 捕捉ELISA で特異的IgM 抗体が陽性であれば、ほぼ確実といえる。HI 試験はCF 試験よりも感度は高いが、海外で感染した可能性のある場合には、その地域で流行している他のフラビウイルス、例えばデングウイルスと交叉反応があるので注 意が必要である。交叉反応が低く特異性の高い方法として中和試験があるが、検査に日数を要する。抗体が上昇する前に死亡した症例では、臨床診断に頼らざる を得ない。
剖検あるいは鼻腔からの脳底穿刺により脳材料が得られた場合は、ウイルス分離、ウイルス抗原の検出、あるいはRT‐PCR 法によるウイルスRNA の検出により、確実な診断となる。血液や髄液からのウイルスの検出は非常に難しい。
治療・予防
特異的な治療法はなく、対症療法が中心となる。高熱と痙攣の管理が重要である。脳浮腫は重要な因子であるが、大量ステロイド療法は一時的に症状を改善することはあっても、予後、死亡率、後遺症などを改善することはないと言われている。
日本脳炎は症状が現れた時点ですでにウイルスが脳内に達し、脳細胞を破壊しているため、将来ウイルスに効 果的な薬剤が開発されたとしても、一度破壊された脳細胞の修復は困難であろう。日本脳炎の予後を30 年前と比較しても、死亡例は減少したが全治例は約3分の1とほとんど変化していないことから、治療の難しさが明らかである。したがって、日本脳炎は予防が 最も大切な疾患である。
予防の中心は蚊の対策と予防接種である。日本脳炎の不活化ワクチンが予防に有効なことはすでに証明されて いる。実際、近年の日本脳炎確定患者の解析より、ほとんどの日本脳炎患者は予防接種を受けていなかったことが判明している。ワクチンは第I 期として初年度に1〜2週間間隔で2回、さらに1年後に1回の計3回、各0.5mlの皮下注射を行うことによって基礎免疫が終了する(3歳未満は 0.25ml)。第I 期は通常3歳で行われるが、その後第II 期として9〜12歳に、第III 期として14〜15歳にそれぞれ1回追加接種を受けることとされている。
感染症法における取り扱い(2012年7月更新)
全数報告対象(4類感染症)であり、診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届け出なければならない。
届出基準はこちら
(国立感染症研究所ウイルス第一部 高崎智彦)