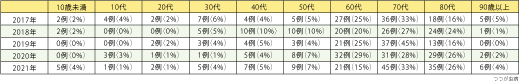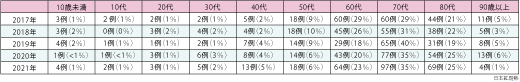お知らせ
感染症情報
研究・検査・病原体管理
サーベイランス
刊行・マニュアル・基準
- 詳細
 注目すべき感染症 ※PDF版よりピックアップして掲載しています。
注目すべき感染症 ※PDF版よりピックアップして掲載しています。
◆ダニ媒介感染症:つつが虫病・日本紅斑熱
ダニ媒介感染症は、病原体を保有するダニに刺咬されることで感染する。つつが虫病と日本紅斑熱は、わが国に常在する代表的なリケッチア症で、リケッチアを保有するダニ類の刺咬による感染症である。両疾患とも、発熱、発疹、刺し口を3主徴とする。感染症法に基づく全数把握の4類感染症であり、診断した医師は直ちに保健所に届け出なければならない(届出基準はhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-04-18.html)、(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-04-23.html)。両疾患の臨床的な鑑別は難しく、届出には実験室診断が必要である。
つつが虫病
つつが虫病の病原体はOrientia tsutsugamushi(以下、菌)と呼ばれるリケッチアで、他のリケッチアと同様に、細胞外では増殖できない偏性細胞内寄生細菌である。本菌には血清型が存在し、Kato、Karp、およびGilliamの3種類の他にも、Kuroki(Hirano)、およびKawasaki(Irie)、およびShimokoshiなども報告されている。媒介するダニ類の一種であるツツガムシは、卵から孵化した後の幼虫期に一世代に一度だけ哺乳動物に吸着し、組織液を吸う。その後は土壌中で昆虫の卵などを摂食して生活する。わが国で本菌を媒介するツツガムシは、アカツツガムシ(Leptotrombidium akamushi)、タテツツガムシ(L. scutellare)、およびフトゲツツガムシ(L. pallidum)の3種のツツガムシが主であり、それぞれのツツガムシの0.1〜3%が菌をもつ有毒ツツガムシである。ヒトはこの有毒ツツガムシに吸着されると菌に感染する。吸着時間は1〜2日で、ツツガムシから動物への菌の移行にはおよそ6時間以上が必要である。菌はツツガムシからツツガムシへ経卵感染により受け継がれ、菌をもたないツツガムシが感染動物に吸着しても菌を獲得できず、自然界でげっ歯類などの動物はヒトへの感染増幅動物とはならない。ヒトは、発生地域の草むらなどで、有毒ツツガムシの幼虫に吸着され感染する。発生はツツガムシの幼虫の活動時期と密接に関係するため、季節により消長がみられる。タテツツガムシ、およびフトゲツツガムシは秋〜初冬に孵化するので、この時期に多くの発生がみられる。また、フトゲツツガムシは寒冷な気候に抵抗性で、その一部が越冬し、融雪とともに活動を再開するため、降雪のある地域では春〜初夏にも発生がみられる。したがって全国でみると、年間に春〜初夏、および秋〜初冬の2つの発生ピークがみられる。また、つつが虫病は広く海外にも存在しており、輸入感染症としても重要である。
つつが虫病の潜伏期間は5〜14日で、典型的な症例では高熱を伴って発症し、皮膚には特徴的なツツガムシの刺し口(黒色痂疲)がみられ、その後数日で体幹部を中心に発疹がみられるようになる。また、患者の多くは倦怠感、頭痛を訴え、患者の半数には刺し口近傍の所属リンパ節、あるいは全身のリンパ節の腫脹がみられる。臨床検査ではCRP強陽性、肝酵素(AST、ASL)の上昇、血小板減少が多くの患者にみられる。治療が遅れると播種性血管内凝固をおこすことがあり、多臓器不全、死に至る場合もある。
病原診断として、確定診断は主に間接蛍光抗体法(IFA)、または免疫ペルオキシダーゼ法(IP)による血清診断で行われている。ある特定の血清型だけに抗体が上昇する場合があるため、複数の血清型の抗原を血清診断に用いることが推奨される。判定は、ペア血清で抗体価が4倍以上上昇した時、あるいはIgM抗体の陽転をもって陽性とする。病原体診断には、刺し口の痂疲、紅斑部皮膚、抗菌薬投与前の末梢血中からの菌のDNA検出が用いられている。
わが国では1950年に伝染病予防法によるつつが虫病の届け出が始まり、1999年4月からは感染症法により4類感染症全数把握疾患として届け出が必須となった。感染症法施行後の症例報告数をみると、2000年は791例が報告されており、2001年には460例に減少したが、ここ数年も400~500例ほどの報告があり、毎年数人の死亡例も報告されている。2017年、2018年、2019年、2020年はそれぞれ447例、456例、404例、539例の症例報告があった。2021年第1~36週に診断された症例数は136例であり(2021年9月15日現在)、2017~2020年の同期間(110例、98例、83例、112例)と比較して多い。報告都道府県別は2017~2021年では鹿児島県が最多で、次いで青森県、千葉県、福島県、宮城県、と続き東北地方や南九州からの報告が多い。報告都道府県の上位5位は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック前の2017〜2019年は、鹿児島県、福島県、千葉県、青森県、秋田県、パンデミックが始まった後の2020年は、鹿児島県、青森県、千葉県、秋田県、宮崎県で、ほぼ同様であった。2021年第1~36週の上位5位は、千葉県、鹿児島県、青森県、宮崎県、山形県であったが、2017~2019年と比べて、特に青森県、千葉県、宮崎県では報告数が多かった。なお、2017~2019年と同様に、全国的には、2020年においても、報告数は第48週、第49週にピークを認めたが、地域差もあり、第19~25週頃にも小規模のピークがみられる。2017~2021年の症例の性別分布は男性が1,173例(59%)、女性が809例(41%)で、年齢中央値は71歳(男性69歳、女性72歳)で60~80代の症例が多かった。新型コロナウイルス感染症のパンデミックの前の2017〜2019年の症例の性別分布は男性が775例(59%)、女性が532例(41%)で、年齢中央値は70歳(男性69歳、女性72歳)であった。2020年は男性が319例(59%)、女性が220例(41%)、年齢中央値は70歳(男性69歳、女性71歳)で同様であった。2021年第1~36週では男性が79例(58%)、女性が57例(42%)で年齢中央値は72歳(男性71歳、女性74歳)であった。なお、2017~2020年は秋から冬にかけて年齢分布が若くなる傾向であった。2017年~2021年の第1~36週までの年齢分布は以下であった。
日本紅斑熱
日本紅斑熱の病原体は偏性細胞内寄生細菌のRickettsia japonica である。ロッキー山紅斑熱など他の紅斑熱群リケッチア症の病原体と同じ属である。媒介ダニは、ヤマアラシチマダニ(Haemaphysalis hystricis)、キチマダニ(H. flava)、フタトゲチマダニ(H. longicornis)などのマダニであることが強く示唆されている。いずれのマダニもヒトへの嗜好性が強い。ヒトは野山に入ったときにこれらのマダニに刺咬され、感染する。全てのマダニがリケッチアをもつわけではなく、リケッチアをもつマダニに刺咬されたときだけ感染する。リケッチアはマダニからマダニへと継卵感染により受け継がれる。また、マダニは幼虫、若虫、成虫のいずれも哺乳動物を刺咬し、吸血する。本症を媒介するマダニは広くわが国に生息しており、発生はマダニの性質や生息域などに影響を受ける。診断月別の症例報告数は、マダニの活動時期と一致し、通常5~10月に多い。発生時期に地域差がみられるものの、その年の天候などの影響も受けるので、全国的に春〜秋の長い間注意が必要である。また、同様の紅斑熱群リケッチア症は広く世界に分布しており、輸入感染症としても重要である。
日本紅斑熱は頭痛、発熱、倦怠感を伴って発症する。潜伏期間は2〜8日と、つつが虫病と比べやや短い。つつが虫病との臨床的な鑑別は困難であるが、つつが虫病では発疹が主に体幹部にみられるのに対し、本症では体幹部より四肢末端部に比較的強く出現すること、またつつが虫病に比べ、刺し口の中心の痂皮部分が小さいなどの特徴があり、刺し口が確認される頻度はやや低い。検査所見では、つつが虫病と同様にCRPの上昇、肝酵素(AST、ALT)の上昇、血小板減少などがみられる。また、急性感染性電撃性紫斑病なども報告されている。さらに、治療が遅れると播種性血管内凝固をおこすことがあり、多臓器不全、死に至る場合もある。
病原診断としての確定診断は、主にIFAやIP法による血清診断で行われている。紅斑熱群リケッチアは種間で血清学的交差反応が強く、R. japonica を抗原として用いれば全ての紅斑熱群リケッチア症の診断が可能であるため、輸入感染症にも対応できる。また、類似疾患の鑑別のため、つつが虫病リケッチアの抗原を併用することが望ましい。病原体診断としては、つつが虫病と同様に刺し口などからのリケッチアDNA検出が行われている。
わが国では1984年に初めて日本紅斑熱の患者の報告がされた。その後症例報告数は1994年まで年間10〜20例程度であったが、2005年頃より増加に転じ、その後は増加の一途をたどっている。発生地域は、1998年以前は鹿児島県、宮崎県、高知県、徳島県、兵庫県、島根県、和歌山県、三重県、神奈川県、千葉県などの報告があったが、以降拡大し、北海道や一部の東北地方を除き全国で発生の報告がみられるようになっている。ここ数年の症例報告数は、2017年は337例、2018年は305例、2019年は318例であったが、2020年は422例と増加した。また、2021年の第1~36週はすでに279例の報告があり、2017年(207例)、2018年(175例)、2019年(162例)、2020年(220例)の第1~36週の症例報告数を上回っている(2021年9月15日現在)。報告都道府県別は2017~2021年では広島県が最多で、次いで三重県、和歌山県、島根県、鹿児島県と続き西日本からの報告が多い。しかし近年では福島県、新潟県、栃木県、茨城県、福井県、石川県等でも患者が報告され、いずれも県内での感染が推定されている。新型コロナウイルス感染症パンデミック以前の2017〜2019年の報告都道府県の上位5位は、広島県、三重県、和歌山県、鹿児島県、長崎県、パンデミックが始まった2020年は、広島県、三重県、島根県、和歌山県、高知県、2021年第1~36週は、広島県、三重県、和歌山県、島根県、鹿児島県、とほぼ同様であった。直近5週間の上位5位は広島県、島根県、兵庫県、三重県、香川県であった。なお、2020年は、2017~2019年と同様に5~10月にかけて報告数が多く、特に9月末から10月にかけて大きな増加がみられた。2017~2021年の症例の性別年齢分布は、男性が783例(47%)、女性が878例(53%)、年齢中央値は72歳(男性71歳、女性74歳)で、60~80代の症例が多かった。2017〜2019年の症例の性別分布は男性が455例(47%)、女性が505例(53%)で、年齢中央値は72歳(男性71歳、女性73歳)であった。2020年は男性が208例(49%)、女性が214例(51%)で、年齢中央値は73歳(男性71歳、女性75歳)であり、2021年の第1~36週までは男性が120例(43%)、女性が159例(57%)で、年齢中央値は72歳(男性69歳、女性73歳)で、新型コロナウイルス感染症のパンデミック以前と以降で年齢分布に大きな違いはみられなかった。2017年~2021年の第1~36週までの年齢分布は以下であった。
終わりに
つつが虫病と日本紅斑熱は、現在も多くの報告がなされ、有効な抗菌薬がありながら、なおも死亡例が報告されている。新型コロナウイルス感染症の流行が始まった2020年以降においても、これらの疾患の症例報告数の減少は認められない。両疾患を予防するワクチンはないので、予防にはダニの刺咬を防ぐことが極めて重要となる。発生時期および発生地を知り、発生地域に立ち入らないこと、農作業や森林作業でやむを得ず立ち入る際には、(1)皮膚の露出を少なくしダニの付着を防ぐ、(2)ダニ忌避剤を使用する、(3)作業後入浴し、洗い流す、などに注意することが必要である。除去できない付着したダニは、医療機関での除去が望ましい。また、両疾患に対する治療は早期に本症を疑い、適切な抗菌薬(第一選択薬はテトラサイクリン系)を直ちに投与することが極めて重要である。重症熱性血小板減少症候群が西日本を中心に近年100例前後報告されており、2016年には、1993年以来となるダニ媒介性脳炎の患者が北海道で発生し、患者は死亡している。さらに、新たなウイルス性のダニ媒介感染症が報告されている。リケッチア症を含む多様なダニ媒介性感染症が出現している中、また、地域差はみられるものの、全国的には例年秋に両疾患の報告数も増える傾向がある中、野外活動をする時には、ダニに対する曝露・感染予防対策が極めて重要である。
つつが虫病・日本紅斑熱に関する詳細な情報については、以下を参照いただきたい:
●日本紅斑熱 1999~2019年
https://www.niid.go.jp/niid/ja/jsf-m/jsf-iasrtpc/9809-486t.html
●つつが虫病・日本紅斑熱 2007~2016年
https://www.niid.go.jp/niid/ja/tsutsugamushi-m/tsutsugamushi-iasrtpc/7324-448t.html
●最近のダニ媒介感染症の国内の発生状況について
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000834837.pdf
●ダニ媒介感染症
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164495.html
国立感染症研究所 感染症疫学センター