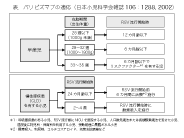(IDWR 2004年第22号掲載)
Respiratory syncytial virus(RSV)は年齢を問わず、生涯にわたり顕性感染を起こすが、特に乳 幼児期において非常に重要な病原体であり、母体からの移行抗体が存在するにもかかわらず、 生後数週から数カ月の期間にもっとも重症な症状を引き起こす。また、低出生体重児や、ある いは心肺系に基礎疾患があったり、免疫不全のある場合には重症化のリスクが高く、臨床上、 公衆衛生上のインパクトは大きい。
疫 学
RSV感染症は世界中に存在し、地理的あるいは気候的な偏りはないが、特徴的なことは、いずれの地域においても幼弱な乳幼児でもっとも大きなインパクトが あることと、毎年特に都市部において流行を繰り返すことである。流行は通常急激な立ち上がりをみせ、2〜5カ月間持続するが、温帯地域においては冬季に ピークがあり、初春まで続く。本邦においても、11〜1月にかけての流行が報告されている。熱帯地域では雨期に流行を見ることが多い。
小児の細気 管支炎や肺炎など、下気道疾患による入院数の増加のほとんどは、RSVの活動 性と一致すると考えられている。もちろん、A型インフルエンザウイルスも同時期に小児におけ る気道疾患の増加する原因となるが、ピークは常に入院の増加につながるとは限らず、ほとんどの場合は、RSV感染症とインフルエンザの流行のピークは一致 しないとされる。
RSVは乳幼児における肺炎の約50%、細気管支炎の50〜90%を占めると報告されており、より年長の小児においても気管支炎の10〜30%に関与し ていると考えられている。一方、呼吸器 症状のない患者から分離されることは滅多にない。通常、すべての新生児では母体からの移 行抗体が母体と同レベル認められるが、徐々に減少し、7カ月以降に検出される抗体は通常、生後の自然感染によるものである。しかしながら、血中で検出され る抗体は即座に感染防御を 意味せず、抗体が存在している生後6カ月以内でもっとも重症化する。最初の一年間で50〜70%以上の新生児が罹患し、3歳までにすべての小児が抗体を獲 得する。肺炎や細気管支炎など のRSVによる下気道症状は、ほとんどの場合は3歳以下で、入院事例のピークは2〜5カ月齢に あるが、最初の3〜4週齢では比較的少ない。また、年長児や成人における再感染は普遍的に 見られるが、重症となることは少ない。
病原体
RSVはParamyxovirus科のPneumovirus属に分類されるエンベロープを持つRNAウイルスであ り、直径80〜350nmの球形、あるいはフィラメント状を呈する。RSV感染により症状を起こす自然 宿主は、ヒト、チンパンジー、ウシであるが、無症状の山羊や羊からも分離される。本ウイルスは 環境中では比較的不安定であり、凍結融解、熱(55℃)、界面活性剤、クロロフォルム、エーテル などで速やかに不活化される。遺伝子配列はすでに決定されているが、分離株間でかなりの差 違があり、大きくA型とB型の二つに分類できる。主要な違いは、もっとも大きな表面の糖タンパ クであるG蛋白に存在する。一般にRSVの流行では、これらの二つの型が同時に認められるが、 地理的、季節的にこれらの比率は様々であり、これがそれぞれの流行において臨床的なインパ クトが異なる原因の一つと考えられており、一般にA型の方が重症になるといわれている。
RSVは環境中では比較的不安定ではあるものの、特に家族内では効率よく感染伝播すること が知られており、乳幼児とより年長の小児のいる家族の場合には、流行期間中に家族の44%が 感染したとする報告もある。概ね家族内に持ち込むのは、軽症の上気道炎症状を来した学童 年齢の小児である。感染経路としては大きな呼吸器飛沫と、呼吸器からの分泌物に汚染された 手指や物品を介した接触が主なものであり、特に濃厚接触を介して起こる。
臨床症状
RSVの初感染は常に顕性であるが、軽症の感冒様症状から重症の細気管支炎や肺炎などの下気道疾患に至るま で、様々である。しかしながら、初感染においては下気道疾患を起こす危険性は高く、69%の乳児が生後最初の一年間でRSVに罹患する。そのうちの1/3 が下気道疾患を起こすと報告されている。2年目から4年目においても下気道疾患を起こす比率は20%を超え、無視できるものではないが、その重症度は年齢 を追う毎に減弱する。乳幼児期早期には肺 炎と細気管支炎が多いが、徐々に気管支炎の病態を呈するものが増加してくる。初感染の病像として、上気道炎や気管支炎の場合でも症状は比較的強い。特に1 歳以下では、中耳炎の合併がよくみられる。生後4週未満ではRSV感染の頻度は低いが、罹患した際には呼吸器症状を 欠く非定型な症状をとることが多く、診断の遅れにつながる。この年齢では、突然死につなが る無呼吸が起きやすいことも報告されており、注意が必要である。
潜伏期は2〜8日、典型的には4〜6日とされているが、発熱、鼻汁などの上気道炎症状が数日 続き、その後下気道症状が出現してくる。発熱は初期症状として普通に見られるが、入院時に は38℃以下になるか、消失していることが多い。咳も主要な症状であるが、持続、増悪する咳 は下気道疾患への進展を示唆する。特に細気管支炎では喘鳴、陥没呼吸や呼吸困難がみら れる。聴診上湿性、乾性ラ音が聞かれる。細気管支炎と肺炎の鑑別は必ずしも容易ではなく、 またしばしば合併する。罹病期間は通常7〜12日で、入院例では3〜4日で改善してくるとされる が、ウイルスの排泄は持続し、ガス交換の異常も数週間続くと考えられている。 胸部レントゲン上では種々のパターンが見られる。もっとも典型的なのは間質性肺炎像と過 膨張であるが、air-trappingが唯一の有意な所見であることもある。肺胞性陰影はRSVによる下 気道疾患の1/4にみられるが、特に6カ月以下の乳児に多い。一般検査所見ではあまり特徴的 なものはなく、白血球数は増加する例もあるが、RSV確定例の20%程度であり、白血球分画も一 定の傾向はない。
RSVの再感染は普遍的に認められ、縦断的な調査では毎年6〜83%の小児が再感染を経験 していると報告されている。通常は軽症の上気道炎や気管支炎であるが、幼児では20〜50%以上の症例で下気道疾患がみられる。成人ではいわゆる普通感冒 を起こすのみであるが、特に、 RSVに感染した小児を看護する保護者や医療スタッフでは、気管支炎やインフルエンザ様症状 をきたし、より重症になることがある。これは、初感染児より排出される大量のウイルスに暴露 されるためと考えられている。また、RSVは高齢者においても、急性のしばしば重症の下気道 疾患を起こす原因として重要になりつつあり、特に、長期療養施設内での集団発生が問題となる。同様に、免疫不全者における院内感染事例では症状が重篤で、 しかもある程度蔓延する まで診断がつかないことが多く、対策を困難にしている。
病原診断
病原体診断は、呼吸器分泌物よりRSVを分離するか、ウイルス抗原を検出することによりなさ れる。鼻腔洗浄液では鼻咽頭拭い液よりも分離率はよいとされるが、このウイルスは熱、凍結融 解、pH、塩濃度、蛋白濃度などに不安定なため、適切な保存液を用い、氷冷して(4℃)迅速に 搬送しなければならない。検体を感受性のあるHEp-2細胞やHeLa細胞に接種することにより、 3〜4日で合胞体の形態を示す特徴的な細胞変性効果を得ることができる。
近年、酵素抗体法や免疫クロマト法による抗原検出、あるいはPCR法による遺伝子検出での 迅速診断法が可能となり、キットも市販されている。抗原検出による迅速診断キットとしては数種 類が利用可能であるが、感度、特異度はいずれも70〜90%で、臨床上有用と考えられる。 血清学的診断は補体結合抗体、酵素抗体法や蛍光抗体法、中和抗体などにより行われるが、 臨床上の価値は高くない。これは、ペア血清が必要なこととともに、特に臨床上問題となる幼 若小児では抗体の上昇が見られないことがあること、年長児の再感染では有意な抗体上昇を 得られないことがあることによる。
治療・予防
治療は基本的には酸素投与、輸液、呼吸管理などの支持療法が中心である。気管拡張剤 およびステロイドの効果については多数の臨床研究がなされている。気管支拡張剤について は、限られた効果にとどまるか、あるいは効果がなかったとする報告が多いが、効果があった とする報告もあり、一定の見解は得られていない。ステロイドについては、症例対照研究で効 果がなかったとの報告がなされている。
米国で唯一治療薬として認可されているのはリバビリンであり、微小粒子のエアロゾルとして 吸入にて用いられる。多数のプラセボ対照研究において、重症度の軽減と酸素飽和度の改善 が認められているが、米国小児科学会では、ハイリスクの患者においてのみ考慮されるべきで あるとしている。RSV感染の致死率は1〜3%と報告されているが、状況によりかなりの差違が あり、基礎疾患、特に心肺系疾患、免疫不全、低出生体重、そして低年齢などが致死率を上げ る危険因子となる。1980年代の心臓に基礎疾患のある小児入院例の研究では、致死率37%と する報告がある。
予防のためのワクチン開発への努力は30年来続けられているが、過去の不活化ワクチンに おいて、接種者が非接種者よりも重症になるという失敗の経験もあり、依然として研究中である。 現在利用可能な予防方法としては、ヒト血清由来の抗RSV免疫グロブリンと、遺伝子組み換え 技術を用いて作成された、RSVの表面蛋白の一つであるF(Fusion)蛋白に対するモノクローナ ル抗体製剤であるパリビズマブ(Palivizumab)がある。後者は日本においても、2001年1月に承 認された。これは、RSV流行開始前から流行期の間、1回15mg/kgを1カ月毎に筋注することに より、予防効果が期待できる。
院内感染は、主に患者との濃厚接触や分泌物に汚染された表面への接触によるので、予防には標準予防策と接触感 染予防策が推奨される。可能であれば、患者の隔離とスタッフのコホーティングも有用である。ガウンとマスクの使用は対照研究では、厳重な手洗いに勝る効果 は 証明されていないが、院内感染率を低下させるとする報告もある。しかしながら、RSVは鼻および眼からも感染すると考えられており、通常の鼻と口を覆うマ スクでは限られた効果しかな いとされる。
感染症法における取り扱い(2012年7月更新)
定点報告対象(5類感染症)であり、指定届出機関(全国約3,000カ所の小児科定点医療機関)は週毎に保健所に届け出なければならない。
届出基準はこちら
(国立感染症研究所感染症情報センター)