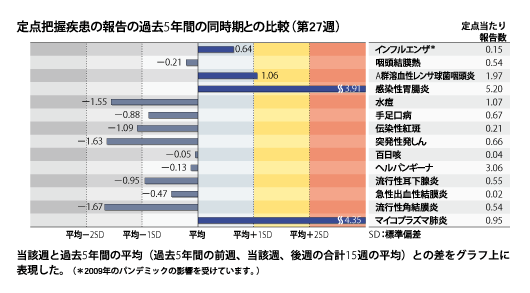お知らせ
感染症情報
研究・検査・病原体管理
サーベイランス
刊行・マニュアル・基準
- 詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈第27週コメント〉 7月11日集計分 ◆全数報告の感染症 注意:これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。 *感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。
全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000 カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000 カ所)、眼科定点(約600 カ所)、基幹定点(約500 カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。 インフルエンザ:定点当たり報告数は減少した。都道府県別では沖縄県(9.67)、鹿児島県(1.06)、宮崎県(0.17)、熊本県(0.14)が多い。 小児科定点報告疾患:RSウイルス感染症の報告数は345例と減少した。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約81%を占めている。咽頭結膜熱の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では佐賀県(1.74)、新潟県(1.18)、福岡県(0.85)が多い。A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は3週連続で減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別では埼玉県(3.13)、福井県(3.09)、山形県(3.00)が多い。感染性胃腸炎の定点当たり報告数は第22週以降減少が続いているが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別では宮城県(10.5)、山形県(9.2)、大分県(7.9)が多い。水痘の定点当たり報告数は第24週以降減少が続いている。都道府県別では長野県(2.19)、福島県(1.92)、北海道(1.90)が多い。手足口病の定点当たり報告数は第19週以降増加が続いている。都道府県別では福井県(4.86)、青森県(4.49)、新潟県(4.45)が多い。伝染性紅斑の定点当たり報告数は横ばいであった。都道府県別では高知県(1.33)、長野県(0.76)、山形県(0.73)が多い。百日咳の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では高知県(0.40)、鹿児島県(0.18)、富山県(0.14)が多い。ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第19週以降増加が続いている。都道府県別では宮崎県(8.75)、群馬県(8.13)、大分県(7.03)が多い。流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では大分県(2.06)、岩手県(1.48)、山形県(1.27)が多い。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 詳細
2012年第27週(第27号)
(7月2日~7月8日)発生動向総覧 /注目すべき感染症(風しん)/病原体情報(ヘルパンギーナ患者から検出されているコクサッキーウイルス 2012年)/海外感染症情報(カンボジアで原因不明の病気の調査結果について) 〔2012年7月23日発行〕
- 詳細
Brucella canis 感染国内症例-名古屋市
(IASR Vol. 33 p. 189: 2012年7月号)
ブルセラ症はブルセラ属菌により引き起こされる人獣共通感染症であり、世界中で発症のみられる感染症である。本邦での報告はまれであるが、輸入感染症や犬から感染した症例の報告が散見する。今回我々はBrucella canis 感染症2例を経験した。感染が発症した背景や感染発生後の対応を含めて報告する。
患者1:71歳男性。高血圧以外には特に既往のないペットショップの従業員。2008年8月に3週間続く発熱と全身倦怠感を主訴に当院救急外来を受診した。来院前に近医では第3世代セフェム系抗菌薬が処方されていたが、症状には改善がみられていなかった。来院時37.8℃の発熱を認めたが身体所見上は特記すべき異常所見はみられず、血液検査では軽度の肝機能障害と腎機能障害、CTでは軽度の肝脾腫を認めていた。入院2日目に入院時に採取した血液培養からグラム陰性桿菌が同定されたため、セフトリアキソン(CTRX)の投与を開始したが症状には改善がみられず、入院5日目に入院時の培養陽性となった菌が培地で発育の悪い球桿菌であるとの情報が細菌検査室から入った。菌の性状や患者背景からブルセラ症を含めた動物由来感染症の可能性が疑われたため、同日からドキシサイクリン(DOXY) 200mg/日の投与を開始し、次第に発熱と全身倦怠感は軽快した。分離された菌株は国立感染症研究所に検査依頼し、PCRの結果からB. canis であることが同定された。血清の抗B. canis 抗体価は1,280倍で陽性であった。B. canis による菌血症であったことが確認されたため、入院10日目からストレプトマイシン(SM)1g/日の投与を追加し、6週間のDOXYと2週間のSMの併用で治療を行った。
患者2:44歳男性、生来健康。患者1の勤務するペットショップの営業者。患者1の症状発症と同一時期から同様の発熱と倦怠感を認めた。同様に近医でホスホマイシン(FOM)などの抗菌薬加療が行われていたが効果なく、患者1の診断確定後に当院での精査を行った。身体所見上は特記すべき所見はなく、血液検査では軽度の肝機能障害を認めるのみであった。本患者も同様に血液培養からB. canis が同定され、血清の抗B. canis 抗体価は320倍であった。DOXY 200mg/日とリファンピシン(RFP) 600mg/日の併用で6週間の治療を行い、発熱と倦怠感、肝機能障害ともに改善した。
上記の2症例はともに発症の2カ月ほど前に流産した犬の胎仔と胎盤の処置をマスクや手袋などの防護なしに行ったとのことであり、その時に感染した可能性が高いと考えられた。保健所の介入もあって、ペットショップの他の従業員や家族、獣医、細菌検体を扱った当院の検査技師についても血液培養、抗体価について検査を行ったがすべて陰性であった。検査に関わった技師3名についてはDOXYとRFPの予防内服を行った。
当該ペットショップの犬37頭(成犬23頭、仔犬14頭)についてもB. canis に対する血清の抗体検査とPCRを施行し、計15頭が抗体、PCRの両方またはいずれかが陽性であり、それらはすべて成犬であった。検査陽性となった犬とその仔犬はすべて安楽殺処分となった。検査陽性となった犬の仔はそれまでに8頭がペットとして買われており、それらの検査結果はすべて抗体、PCRともに陰性であった(次項参照)。
ここに報告した2症例は特異的な症状を示さず不明熱の様相を呈していたが、血液培養からの菌検出により診断することができた。2症例とも抗菌薬の併用治療により良好な治療経過であった。保健所の介入もあり、動物や感染者と濃厚接触のあった従業員や家族、菌に曝露した検査技師についても抗体検査、PCRを施行した。またブルセラ症は検査室での感染のリスクも高いため、曝露した検査技師3名には抗菌薬の予防投与を行った。
1999年にブルセラ症が4類感染症になって以降、本症例の報告までにヒトのB. canis 感染症は7例の報告があった。ヒトのブルセラ症は慢性の経過で特徴的な症状を呈さないことも多く、B. canis 感染症の場合には感染源となっている犬もブルセラ菌感染による症状が軽微か無症状であることが多い。このため、ヒトのB. canis 感染症は診断のなされていないケースも多いと考えられ、実際はより多くの感染例があるものと考えられる。感染の伝播を防ぎ、感染した場合に対して早期に対応できるようにするためには、ペットを扱う業者や飼育者、医療者へのB. canis 感染症に対する知識の普及が重要であると考える。
1)今岡浩一, モダンメディア 55: 76-85, 2009
2) Nomura A, et al ., Emerg Infect Dis 16: 1183-1185, 2010
中部ろうさい病院リウマチ膠原病科 野村篤史 藤田芳郎
同 腎臓内科 志水英明
同 細菌検査室 今西 一
- 詳細
日本におけるブルセラ症
-感染症法施行前(1999年3月31日)まで-
(IASR Vol. 33 p. 186-187: 2012年7月号)
日本で、ブルセラ症が感染症法により届出疾患となる以前(~1999年3月31日)の患者について文献報告を元に調査した。その結果を表1に示す。
国内での最初の症例報告は、1933年に西川が報告した京都でのBrucella abortus 感染と思われる女性の症例である1) 。その当時、京都府では菌を保有する牛が20%、また、感染牛を飼育する牧場は82%にもおよぶ牛ブルセラ病流行地域であった。患者は、牛乳を温めて飲用していたが、殺菌目的の加熱は行っておらず、そのため感染したと考えられた。診断は凝集反応により行い、家畜ブルセラ菌特異的抗体が検出されている。
*B. abortus 感染症は、1897年に牛の流産胎仔からB. abortus を発見したBangにちなんで、バング氏病と呼ばれていた。また、国内の牛からの最初の菌分離は1916年であり、国内に蔓延していた。
その後、1962年に鶴見が1933~1962年までの報告を調査し、まとめて発表している2) 。それによると、上述した症例を含めてこの間に男性34名、女性17名の51例の報告があり、このうち6例が死亡したとされている。患者の年齢は20~40歳が多くなっていた。国外感染・発症後帰国が3例、患者検体の検査等による検査室感染が13例と非常に多く、その他国内で感染したと推定されるものが34例である。これら症例のうちB. melitensis 感染は、検査室感染を除きすべて輸入症例であった。家畜関係の職業に従事している者に多い傾向があった。症状は、波状熱、全身倦怠感などで、死亡例は心内膜炎、敗血症、脊椎ブルセラ症などであった。
*B. melitensis は過去から現在まで国内の家畜で感染報告はない。
その後も報告が散見されるが、渡航歴が無く、国内で感染したと考えられるB. abortus 感染症例3-5) もある。
B. melitensis 感染では、海外で感染し、帰国後に国内で発症した輸入症例が報告されている。渡航先はインドとイラクで、いずれもブルセラの常在地域である6,7) 。インドで感染した患者のケース(1980年)では検査担当者が検査室感染を起こし、それぞれ2カ月、4カ月にわたり血液から菌が分離されている(IASR 16: 127, 1995参照)。抗体価も高値を示したが、菌が分離された期間を過ぎると下降していった6) 。
イラクで感染した患者の場合(1998年)は、夫婦で感染するという特異な感染事例となった7,8) 。夫は、イラク旅行の1カ月後より発症し、発症後3カ月目に検査したところ抗体陽性であったことからブルセラ症と診断された。妻は、夫の発症から約2カ月遅れて発症し、受診時には夫が診断後であったため即時にブルセラ症を疑い確定している。ただ、妻には海外渡航歴が無く、本症例は、非常にまれとされているヒト-ヒト感染であったと推定されている7,8) 。その後、どちらの症例からも菌が検出され、同定されている。
さらに特異な感染事例として、母親が妊娠中にペルーで発症・治療(3週間の投薬)を受けた後、日本国内でその子供が発症するといった症例(1995年)が報告されている5) 。患児は1歳7カ月の時に発症(高熱)し、血液および骨髄液からB. abortus が分離された。27週、916gという早産・低出生体重ではあったが、出生時からそれまでには、持続する発熱など明らかな異常は見られていなかった。先天性のブルセラ症か経乳感染したのかは明らかにはなっていない。凝集反応では患児、母親ともに疑似と判定され、抗体価は高くなかったが、母親の方が若干、高値を示していた。投薬により寛解している。
B. canis 感染については持続的発熱、体重減少、頸部リンパ節腫脹を示し、B. canis に対する抗体が陽性となった報告が1例のみ見つかった9) 。しかし、繁殖施設でイヌのブルセラ病の流行が多発した1970年代(表2)に実施された、ヒトのB. canis に対する抗体調査の報告によると、ヒトにおける抗体保有率は東京都民3.9%(40/1,017)、飼育管理者30%(7/23)であり、その他の報告を含めても2.0%(69/3,440)となっている10) 。また、報告としては残っていないが、当時はB. canis に実験室感染した例も少なからずあったと伝えられている。
*B. canis は、米国のビーグル犬繁殖施設で流産が多発し、1966年にCarmichaelによりその原因菌として分離・報告された。日本でも最初は実験用ビーグルの繁殖施設で流行したが、その後、一般のイヌでも感染が見られるようになっていった。
参考文献
1)西川治良兵衛, 東京医事新誌 2843: 23-24, 1933
2)鶴見等, 日本伝染病学会雑誌 36: 201-204, 1962
3)武田 勇, 他, 病理臨床 23: 486, 1975
4)Takahashi H, et al., Internal Med 35: 310-314, 1996
5)小久保稔, 他, 日本小児科学会雑誌 101: 1067-1070, 1997
6)伊佐山康郎, 他, 日本細菌学雑誌 37: 336, 1982
7)寺田一志, 他, 臨床放射線 44: 953-956, 1999
8)Kato Y, et al., J Travel Med 14: 343-345, 2007
9)室豊吉, 他, 綜合臨床 30: 549-552, 1981
10)伊佐山康郎, 獣医畜産新報 47: 97-101, 1994
国立感染症研究所獣医科学部第1室 今岡浩一 木村昌伸
- 詳細
腸腰筋膿瘍を呈したBrucella melitensis 輸入感染症例
(IASR Vol. 33 p. 187-188: 2012年7月号)
はじめに
ブルセラ症は、ブルセラ属菌により引き起こされる世界的に重要な人獣共通感染症である。中南米・メキシコ・アラビア海沿岸・インド・東南アジアの地域に患者が多い。国内では、感染症法により全数届出となった1999年4月~2012年3月に19例が届け出られている。国内では家畜対策が功を奏し、家畜ブルセラ菌(Brucella melitensis 、B. abortus 、B. suis)感染例は現在では輸入患者に限られている。主症状は通常、発熱、倦怠感、背筋痛、関節痛などインフルエンザ様で特徴が少なく、症状のみでは診断が困難である。また、まれに骨髄炎、心内膜炎、中枢神経症状などの合併症を示すこともある。今回は、B. melitensis による腸腰筋膿瘍を呈した輸入患者を経験したので報告する。
症例:48歳、女性、ペルー人
主訴:腰痛
現病歴:2009年10月にペルーに帰国し、現地のチーズや肉を食していた。ペルー産のチーズを日本に持ち帰り、夫と子どもも食していた。12月頃から腹痛があり当院内科を受診し膵炎の疑いがあり、内服にて経過観察していた。2010年2月21日、腰痛を訴えて当院救急外来を受診した。3月31日、CT画像上腸腰筋膿瘍(図1)を疑い、整形外科入院となった。MRI検査で第3・第4椎間板炎を認めた。椎間板穿刺液と腸腰筋内の膿が培養検査に提出された。Stapylococcus aureus の感染を疑いフロモキセフ(FMOX)の点滴を開始した。4月2日38℃の発熱があり、血液培養を開始した。再度腸腰筋内の膿を15ml吸引し、培養に提出された。
血液検査:WBC 8,200/μl、CRP 14.25 mg/dl
微生物検査:4月2日の膿の外観は白血球を多く含む橙赤色で粘調性のあるものだった。塗抹・培養は当初ともに陰性だったが、培養を継続したところ、4月5日チョコレート寒天培地に微小なコロニー(図2)とGAM半流動培地の上層部に濁りを認めた。グラム陰性小桿菌が観察された(図3)。サブカルチャーにて増菌したが、当院の同定キットでは同定できず、4月7日岐阜大学の大楠准教授に相談したところ、Brucella菌の疑いが強いと助言をいただき、翌日、行政検査として国立感染症研究所に検体を送付し、ブルセラ属菌特異的PCRによりB. melitensis と同定(図4)された。なお、同時に送付した血清を用いた試験管凝集反応でも、B. abortus に対して80倍陽性、B. canis に対して320倍陽性と、B. melitensis 感染の特徴を示していた。
治療:当初、S. aureus 感染を疑い、FMOXを使用していたが、B. melitensis の疑いがあるという情報を得たので、リファンピシン(RFP)内服とミノサイクリン(MINO)とゲンタマイシン(GM)点滴投与に変更した。解熱したが膿量の減少はみられなかった。透視下で穿刺を行い、膿の吸引とMINOの注入を3カ月継続したが膿の減少を認めなかった。しかし、その後の培養は陰性であった。7月27日からシプロフロキサシン(CPFX)点滴投与を追加し、膿瘍の減少を認めた。9月1日に退院し、その後炎症反応と血沈が完全に陰性化するまでRFPとMINOの内服を7カ月継続した。
検査にかかわる医師、技師の感染対策
膿の吸引は、放射線科の透視下で実施したので、Brucella 菌の疑いがあるという情報を放射線科へ伝え、ゴーグル付きマスク、ディスポーザブルエプロン、手袋を着用の上、実施してもらった(図5)。Brucella 菌が疑われる前に、微生物検査室の技師は、培地のにおいを嗅ぐという行為を行ってしまった。Brucella 菌は、安全キャビネットが広く使用されるようになる前は実験室感染が多い菌として知られており、培地のにおいを嗅ぐ行為も感染リスクを伴う。そのため、検査従事者には、抗菌薬の予防内服(RFPとMINOの3週間内服)が行われた。
感染症法
ブルセラ症は、4類感染症であり、診断した医師は最寄りの保健所長を経由して直ちに都道府県知事に届け出なければならない。また、B. melitensis 、B. abortus 、B. suis 、B. canis は三種病原体に指定されている。今回のケースでは、B. melitensis 感染と診断されるとともに保健所に届出、また、当院にて保持されていた分離菌株は滅菌廃棄処置を行った。
まとめ
今回、当初は塗抹陰性と報告したが、菌名がわかってから再度塗抹を鏡検したところ、桿菌らしきものが認められた。ブルセラ属菌は非常に小さく、日本ではなじみもないことから、ややもすると見落としがちにもなる。ブルセラ症流行地への海外渡航歴があり、不明熱等ブルセラ症様の症状を示している場合は、ブルセラ症も念頭に置いて、注意深く検査しなければならない。また、コロニーのにおいを嗅ぐという行為は微生物検査上、重要な情報を与えてくれる。しかしながら、検査室では安全キャビネットは通常使用されておらず、このようなケースでは、検査上日常的に行われている行為が危険をもたらすことを認識した。なお、持ち込んだチーズはすべて食されており、検査不能であったが、これらを食した夫と子どもには症状は見られず、患者はペルーに帰国時に感染したと考えられた。
豊川市民病院臨床検査科微生物検査室 森田さゆり 峯田有美子 浅井蓉子 松岡好之
豊川市民病院整形外科 長原正静
- 詳細
Brucella canis 感染症発生時の行政対応について―名古屋市
(IASR Vol. 33 p. 189-191: 2012年7月号)
2008(平成20)年、名古屋市内でBrucella canis 感染症患者が発生した。これは、ペットショップで繁殖用として飼われていた犬から感染したもので、B. canis 感染症と診断された患者から菌が分離された国内初の事例となった(前項参照)。以下、患者発生後の行政対応等について報告する。
1.初期対応
平成20年8月、医師から市内保健所にブルセラ症患者発生の届出があった後、保健所は医師および患者(入院中)からの聞き取り調査と、患者(以下、「従業員A」)の勤務先であるペットショップ(犬・猫等の販売、犬の繁殖とトリミング、ペットホテル等)への立ち入り調査を行い、従事者の健康状態や従事状況、犬の健康状態や管理方法、犬の繁殖・販売状況、清掃・消毒の実施状況等について確認した。
従業員Aは、ペットショップで犬の出産介助等に従事しており、店の犬から感染したことが疑われた。このため、保健所は、営業自粛、施設の消毒、感染防止措置の徹底、犬の単独飼養(1頭ずつ個別に飼養)等を指導した。ペットショップは、犬に関する営業を自粛するとともに、施設の消毒を行い、作業時におけるマスク・手袋の着用等の措置を行った。さらに、店舗内を区画して来店者が犬に触れないよう隔離し、犬は単独飼養とした。
また、保健所は、営業者、従業員および営業者の子供(ペットショップに連れてこられていたため)ならびに飼養犬全頭(37頭)の血液検査を実施した(検査は国立感染症研究所)。
2.検査結果
(1)営業者、従業員および営業者の子供:検査結果を表1に示した。営業者と従業員Aはともに抗体検査が陽性で、血液から菌が分離されたことから、B. canis への感染が判明した。また、発症時期についても同時期であった。
(2)犬:初回の検査結果を表2に示した。犬37頭中、繁殖用成犬14頭が陽性、販売用子犬はすべて陰性であった。陽性犬のうち、抗体陽性・遺伝子検出・菌分離すべてに該当したものが2頭、抗体陽性で遺伝子検出されたもの(菌分離されず)が3頭、抗体陽性で菌分離されたもの(遺伝子検出されず)が3頭、抗体のみ陽性であったものが2頭、遺伝子のみ検出されたものが4頭だった。
3.感染経路
(1)犬:明らかな死・流産はなかったことから、ペットショップに菌が侵入したのは患者発症の数カ月前ではないかと考えられ、平成20年1月以降の交配歴や出産歴等をたどった。しかし、犬の仕入れ先や交配先が多数であったこと、感染が判明したときには既に多数の犬が感染していたことから、いつどこからペットショップに菌が侵入したのかを推察することはできなかった。
(2)営業者と従業員A:営業者と従業員Aは、平成20年6月に感染犬の出産介助をしていた。その際、出産予定日に出産されたものの胎膜が破られずに放置されていたことに気付き、マスクをせず素手で胎膜を破って胎仔を取り出す作業をしていた。なお、その時点で子犬は死亡していたが、死産であったのか出生後に死亡したのかは不明とのことであった。患者2名は発症時期が同時期であったこと等から、この際、感染犬の胎盤等と濃厚接触したことにより感染したのではないかと推測された。
4.検査結果を受けた対応
保健所は、感染犬と非感染犬を分けて飼養し、非感染犬については単独飼養を継続するよう追加指導したところ、ペットショップはこれらの措置を行った。
本市は、感染犬と関連のある他のペットショップ等(犬の販売・交配先、ペット市場)を管轄する行政機関に情報提供し、同時にペットショップからも販売・交配先およびペット市場に情報提供した。個人に販売されていた犬についてはこのペットショップが検査し、それ以外の販売先・交配先の感染犬と関連のある犬については各々の店舗が検査し、感染していないことが確認された。
また、本市は、市内の犬繁殖業者への感染防止措置の徹底を指導するとともに、注意喚起を目的として本件について公表した。ただし、犬の管理が可能で感染防止措置がとられていたこと、調査が実施可能であったこと、患者のプライバシー保護の観点から、ペットショップについては公表しなかった。
さらに、本市は地元獣医師会やペット関連組合等に対して、厚生労働省は全国自治体・環境省・獣医師会等関連団体に対して、情報提供と注意喚起を行った。
5.その後の経過
(1)患者:初回検査の約1カ月半後、医療機関で検査したところ、営業者は抗体価320倍、従業員Aは1,280倍と、初回検査結果から変化がなかった。さらに1カ月後の検査では、営業者は160倍、従業員Aは320倍と低下したことが確認された。
(2)犬:初回検査で感染が確認された犬は、ペットショップの判断により動物病院で安楽死された。また、初回検査で陰性であった犬23頭のうち16頭について、約1カ月半後に動物病院で2回目の検査を実施したところ、新たに成犬1頭の感染が確認され(抗体陽性、菌分離)、安楽死された。その後、このペットショップは廃業したため、これ以降の検査については実施されなかった。
6.最後に
B. canis のヒトへの感染事例が稀なことから、B. canis 感染症に関する情報は少なく、被害拡大防止措置等の対策に苦慮したものの、本事例はペットショップの理解と協力により、原因追求・感染拡大防止措置を行うことができた。人獣共通感染症についての知識や感染防止のための注意事項を啓発する必要性については再認識したところであるが、動物取扱業界自らのB. canis 清浄化への努力も望まれるところである。
名古屋市健康福祉局食品衛生課(現名古屋市農業センター) 堀越喜美子